まずは、悪い知らせのほうから。
『芸術新潮』 2015年5月号より、足掛け3年にわたった連載 「マンガ展評 ちくちく美術部」 が・・・


2018年3月号をもって、最終回を迎えます!!
1年で終わる予定でしが、気づけば、また1年、
さらに1年と、結果的に3年間も連載を続けさせて頂いたのは、本当に奇跡のようなこと。
テレビっ子の自分としては、青春を捧げたバラエティ番組である 『みなさんのおかげでした』 と、
『めちゃイケ』 の最終回と同じタイミングで、最終回を迎えられるのも、感慨深いものがあります。
ちなみに、どうしても一つだけ言っておきたいことが。
先々々月の 「マンガ展評 ちくちく美術部」 は、
特集号であったため、担当の副編集長が忙しかったという理由でお休み。
先月号は、副編集長が風邪を引いたという理由でお休みでした。
休載→復活→休載→最終回というグダグダっとした流れですが、
決して、僕やいのっちさんが何かの不祥事を起こして、打ち切りとなったわけではありません。
晴れて、部活を卒業する形です。
涙なしには読めない (?) 最終回、どうぞお楽しみに。
ではでは、良い知らせのほうを。
最終回の翌月に発売される2018年4月号にて、
10ページの特集企画が組まれます!!
それは、最終回の打ち上げの席でのこと。
アートテラーとして今年10周年を迎えるにあたり、
この5月に実行しようとしていた 『水曜日のアートテラー』 の企画を副編集長に話したところ・・・
「それ、うちの特集ページでやろう!」
と、まさかの提案。
あれよあれよと、編集会議も通ったそうで、
本当に 『芸術新潮』 の紙面を使って、検証される運びとなりました。
その説が、こちら↓

今から遡ること、10年前。
まだブログは始めておらず、mixiの日記で情報を発信していた時代に、
「人は一日で、いくつの美術展をハシゴすることができるのか?」 を検証したことがありました。
ルールは、2つ。
・1館につき、滞在時間は30分
(多くの美術館が閉館時間の30分前に入館を締め切っている。つまり、30分が必要最低美術鑑賞時間と考えられる)
・移動は公共の交通機関を利用しなければならない
(自家用車やタクシー、自転車での移動はNG)
そのチャレンジの際に生まれた記録が、18館。
おそらく、ギネス記録です (笑)
(その模様は、当時のmixi日記で読めます→50回記念特別企画 “とに~のめっちゃ美術展へ行こう!”スペシャル)
さて、あれから10年。
東京に限って言えば、誰よりも美術館情報に精通しているという自信があります。
さらに、国宝ハンターなどの数々の過酷な企画を経て、体力や精神力にも自信があります。
10年経って成長した今の自分ならば、
19館という新記録が達成できるというのが、今回の説の趣旨でした。
入念にタイムスケジュールを組んだ結果、
5月のとある金曜に開催すれば、少し余裕をもって19館は巡れるはずだったのですが。
入稿などもろもろの関係で、ロケ日は明日2月16日に決まりました。
実は、この日は、理想の行程で要となる国立西洋美術館、上野の森美術館、根津美術館、
東京芸術大学大学美術館、東京ステーションギャラリー、21_21 DESIGN SIGHTがのきなみ休館日。
もっとも難易度が高い日なのです。
再検討した結果、一か所余分にエリアを巡らなければならないことになりました。
そのため、電車移動が増える→移動に裂ける時間が削られる→移動はすべてダッシュということに。
「詳細は2018年4月号にて」 ということで、
タイムスケジュールはここでは発表できませんが。
超過密なハードスケジュールとなっています。
もっとも難関なのは、とある美術館から、とある美術館への移動。
直線距離にして1.6㎞の道のりを、13分で走破しなくてはなりません。
それ以外の移動も、1分でも遅れたら、19館という記録の達成は不可能。
企画としては、その時点で終了です。
アートテラー人生でもっとも過酷なチャレンジにして、
もっとも失敗できない一世一代の大勝負といえるでしょう。
ちなみに。
副編集長的には、最後の最後まで、
「1館巡るたびに、図録が1冊増えると面白い!」 と、図録ルールなるものを採用するつもりでいました。
シミュレートで図録7冊を背負って、走ってみましたが、3分が限界。。。
なんとか、そのルールを撤廃して頂きました。
いや、18冊の図録を持って移動しろって、どんだけ鬼なんだ。
1位を目指して、ランキングに挑戦中!
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!




































































































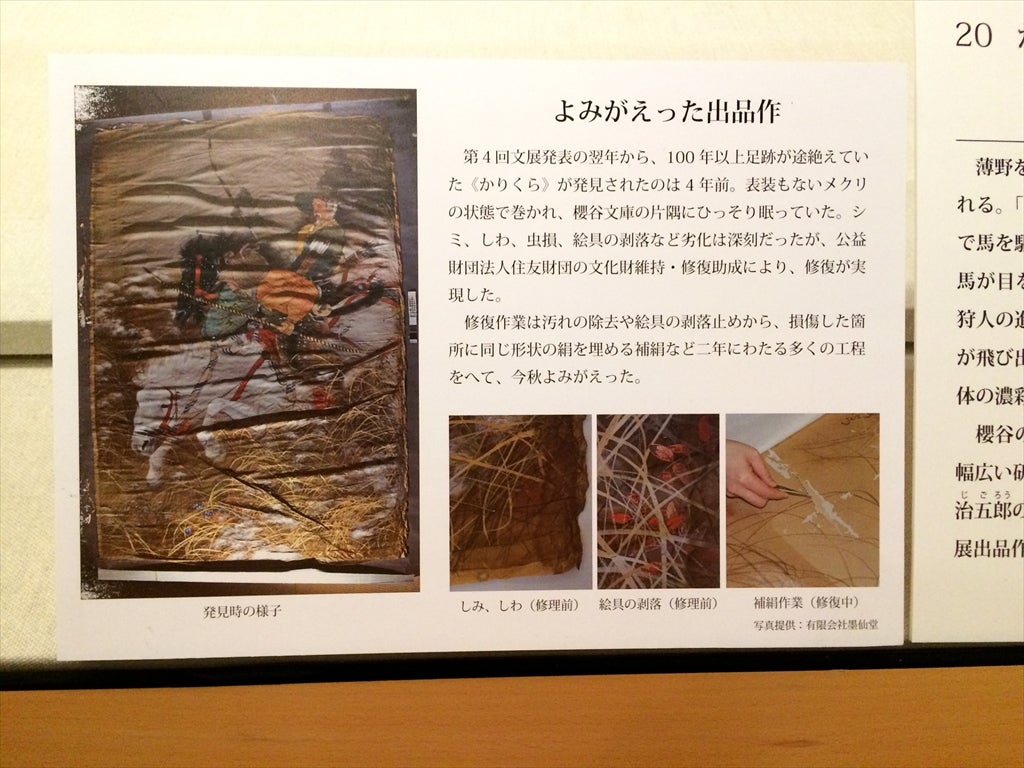















































 ”
”

































