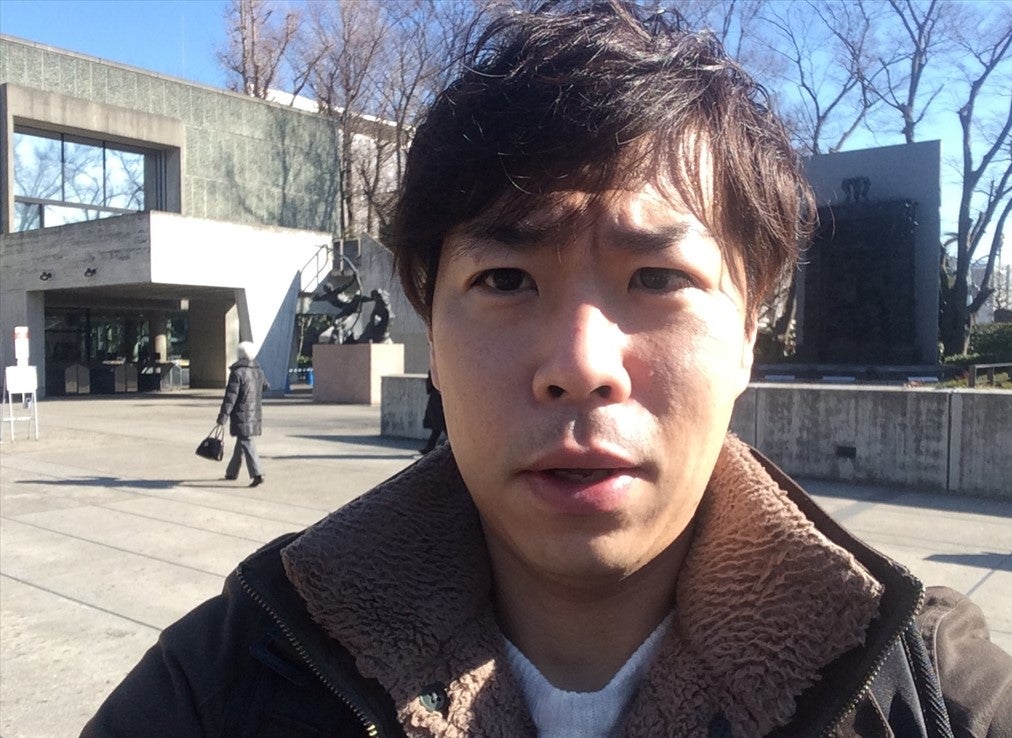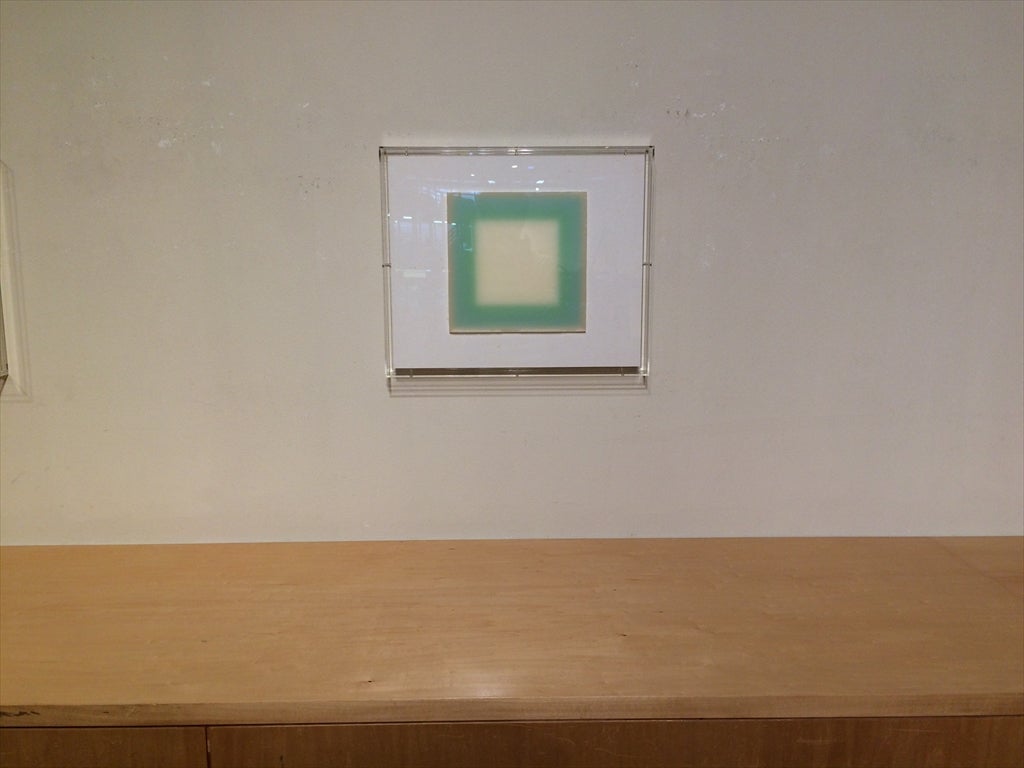アートテラー・とに~が信じる美術に関する説を検証していく企画 『水曜日のアートテラー』。
2018年も攻めの姿勢で、いろいろな説を検証しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、以前、この企画の元ネタ 『水曜日のダウンタウン』 で、
バイきんぐの小峠さんが体を張って、このような説を検証していました。
「芸能人の名前に入っている食べ物しか食べられなくても 1週間はギリ生きられる説」馬場典子さんに会ったら、馬。
サンドウィッチマンに会ったら、サンドウィッチというように、
会った芸能人の名前に入っている食べ物しか食べられないという企画でした。
結果的には、食べ物の名前をコンビ名にしている若手芸人が多いことが判明し、
企画開始5日目にして、これ以上検証する必要はないのではと、強制的に終了していました。
・・・・・と、そこで今回は、この説のアートテラーver.を提唱したいと思います。
![説]()
例えば、フェルメールの
《牛乳を注ぐ女》 を観たなら、
牛乳と
パンを、
![牛乳]()
高橋由一の
《鮭》 を観たなら、
![鮭]() 新巻鮭
新巻鮭を食べることが出来ます。
ちなみに、浮世絵などの版画作品は食べ物が多く描かれていそうなので、今回の検証は、絵画限定。
さらに、心優しいギャラリストさんが僕のために、
食べ物が描かれた絵画を展示してくれることも無きにしも非ずなので、美術館限定とします。
果たして、このルールのもと、1週間を無事に乗り切ることができるのか!?
2018年1月11日。
【検証1日目】![とに~]()
まずは、確実なところで、国立西洋美術館にやってきました。
こちらの常設展には、必ず何かしら食べ物が描かれた絵画があるはずです。
![常設展]()
と、予想は的中。
会場を訪れてものの数分で、食べ物が描かれた絵画を発見しました!
![キリスト降誕]()
ロレンツォ・レオンブルーノ・ダ・マントヴァという画家の
《キリスト降誕》 です。
![母乳]()
このチャレンジ企画の記念すべき1発目の食べ物は、まさかの母乳。
「母乳なんて、絶対に手に入らないよなァ・・・。」
そう、もし絵画の中で食べ物を見つけたとしても、
その食べ物を調達できなければ、食べることは出来ません。
また、
《キリスト降誕》 には、牛が描かれていますが、
明らかに食材として描かれていないので、牛肉を食べることは出来ないのです。
気を取り直して、館内を探索。
予想に反して、食べ物が描かれた絵画が見つかりません。
気弱になりかけた次の瞬間。
「あったーー!!」思わずテンションが上がる僕。
絵のもとに駆け寄ります。
![食材]()
こちらは、フアン・バン・デル・アメンというスペインの画家が描いた静物画。
《果物籠と猟鳥のある静物》 です。
ブドウ、
モモ、
メロン、
ザクロなどフルーツをまとめてゲット。
ついでに、
よくわからない鳥もゲットです。
さらに、その絵の近くに、もう一点似たような主題の静物画がありました。
アドリアーン・ファン・ユトレヒトの
《猟の獲物と野菜のある静物》 。
![猟の獲物と野菜のある静物]()
再び、
よくわからない鳥を大量にゲット。
どこで売っているかわかりませんが、
ウサギと
アーティチョークもゲットしました。
とりあえず、今夜は何かしらの鳥の肉は食べられそうです。
ルンルン気分で、お馴染みの
鳥博士・高橋君にLINE。
すると、衝撃の答えが返ってきました。
「
《果物籠と猟鳥のある静物》 に描かれてるのは、
シロハラサケイ (ヨーロッパや北アフリカに生息) と
アカアシイワシャコ (イベリア半島のみに生息)。
《猟の獲物と野菜のある静物》 に描かれてるのも、ほとんど日本にいない鳥だよ」
絶対、調達できないじゃん (泣)。
しかし、まだ希望はあります。
「でも、
《猟の獲物と野菜のある静物》 の真ん中にキジがいるよね?」
キジ肉ならば、探せば調達できそうです。
「それは
コウライキジで、日本のキジとは別種」
・・・・・・・・・・・・・。その後、美術館をくまなく探し回りましたが、見つかるのは、フルーツばかり。
![フルーツ]()
![フルーツ]()
![フルーツ]()
お腹にたまりそうなもの、のどを潤せそうなものには出会えません。
かろうじて発見したのは、パン。
ミレーの
《春(ダフニスとクロエ)》 をじーっと観ていたところ・・・
![ミレー]() カバン (?) の中にパンが入っていました!
カバン (?) の中にパンが入っていました!![パン]()
これまで何十回と常設展を訪れていますので、
この作品も何十回と目にしているはずなのですが。
パンが描かれていることに初めて気が付きました。
これぞ執念です。
国立西洋美術館をあとにし、食材探し。
“ひとまず水分は確保しないといけないし、フルーツは多めに買っておこう!”
と、スーパーに向かいました。
しかし、青果コーナーに足を踏み入れた瞬間、とんでもない事実に気づかされるのです。
「モモもスモモもザクロもサクランボもないじゃん!」そう、今は1月。
西洋絵画で描かれがちなフルーツは、旬じゃないのです。
売り場にあったのは、リンゴやミカン。
そんな絵、無かったわ。
何でこの企画を、今の時期にやることにしたんだ!バカヤロウ!と、まだまだ自分を責めたいところですが、
0時から飲まず食わずなので、怒る気力も底をつきかけています。
ひとまず買えるものを購入し、帰宅。
企画開始初の食事にありつきました。
![ブドウ]()
![パン]() 「美味いっ!」
「美味いっ!」気力がチャージされましたので、再び買い出しへ。
夕食となる食材を探しに行きました。
しかし、なかなか見つからず。
数多くのスーパーを巡り、最終的に、青山の紀伊国屋インターナショナルにて、
![紀伊国屋]() ウサギ
ウサギと
アーティチョークを調達しました。
どちらも人生で初めて手にする食材です。
恐る恐る調理。
![食材]()
![調理]()
で、恐る恐る食事。
![調理]()
![食事]() ・・・・・お腹が空いているので、何でも美味しく感じました (笑)
・・・・・お腹が空いているので、何でも美味しく感じました (笑)さてさて、この企画は、本日 (1/11) 始まったばかりです。
なんとか、1週間後の水曜日 (1/17) まで、無事にチャレンジし続けたいと思います。
応援のほど、よろしくお願いします。
「食べ物が描かれた絵画なら、あの美術館にありましたよ」
そんな情報を、心よりお待ちしております。
「うちで展示してるよ」 という美術館の方からの情報も大歓迎です。
とりあえず、今は、お米と水分を身体が欲しています (笑)
1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です![アップ]() )
)
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!![Blogランキングへ]()
![にほんブログ村 美術ブログへ]()













 )
)