美術品を手に、銀座を代表するギャラリーの数々を訪問し、
昔話 『わらしべ長者』 のように、物々交換してもらおうという企画。
それが・・・
![わらしべ]()
我が家に田中田鶴子による謎の抽象画が棲みついて(?) から、早1ヶ月が経ちました。
![田中]()
出会った当初は、「暗い絵だなぁ。。。」 という印象しか抱けませんでしたが。
毎日、眺め続けていれば、きっと新たな気づきもあるはず。
そう思っていたのですが、結局のところ、今日の今日まで印象は変わりませんでした。
終始、“暗い絵だなぁ。。。” のまま。
おそらく、あと1年くらい飾っていても、その印象は変わることはないでしょう。
このままでは、心がどうにかなってしまいそうなので (?)、作品を交換してもらうことに。
そこで、今回は、GINZA SIXの真向かいにある・・・
![]()
”心と眼を大切にする”
至峰堂画廊銀座店にご協力を仰ぎました。
![]()
![]()
もともとは、1977年に大阪で開設された至峰堂画廊。
今も大阪店は現役ですが、銀座店は2009年にオープンしました。
創業者の息子である鈴木庸平さんが、そのオーナーを務めています。
![]()
そんな至峰堂画廊が特に力を入れているのが、日本近代洋画。
明治から昭和にかけて活躍した物故作家の作品に、思い入れが強いそうです。
応接室には、さらっと藤島武二と坂本繁二郎の作品が飾ってありました。
当たり前ですが、もちろん本物です。
さてさて、これまでの 『わらしべ長者生活』 企画の経緯を、
ちゃんとブログでチェックしてくれていた鈴木さんより、まずはこんな提案がありました。
「とに~さん、そろそろ企画的にインフレがあったほうが面白くないかな?」
「いや、まぁ、もしそうなったら、僕としては願ったり叶ったりですけど」
「田中田鶴子さんの作品と、どれを交換したらいいか考えていたら、候補がいろいろ出てきてね。
で、それらの作品を今から全部見せるから、とに~さんが最終的に1点を選ぶってのは、どうだろう?
中にはインフレする (=値段が何倍にもなる) 作品もあるし、反対にデフレとなる作品もあるよ」
さすが大阪出身 (←?)、サービス精神旺盛な鈴木さん。
オモロイ趣向を用意してくれていました。
ここは是が非でも、今回の交換でインフレを起こしたいところです。
それでは、今から登場する作品の中で、
もっともインフレする高額な作品はどれなのか、
皆様も一緒にお考えください。
①ラグーザ玉 (1861~1939) の水彩画![]()
鈴木さん曰く、世界的にも活躍した女性作家繋がりで選んだ一枚。
日本に西欧美術を伝えた彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザの妻であり、
日本初の女性西洋画家として知られるラグーザ玉が描いたチューリップの絵です。
画面の左半分が紙焼けしていますが、むしろそれすら味に感じます。
②小磯良平 (1903~1988) のエッチング![]()
日本を代表する洋画家のひとり、小磯良平のエッチング作品。
ちなみに、この作品を鈴木さんが選んだ理由は、
小磯良平は、田中田鶴子が属した新制作協会の立ち上げメンバーの一人であるから。
それと、小磯作品は品が良いので、畳の部屋にも合いそうだからとのこと。
ブログを通じて、部屋の雰囲気までチェックしてくださっていたとは。
③石川欽一郎 (1871~1945) の水彩画![]()
こちらも、僕の畳の部屋に合いそうな一枚とのこと。
日本では、ほとんどその名が知られていない石川欽一郎ですが・・・。
2期に渡って台湾で美術教育に携わったというその功績から、
台湾では、知らない人はいないであろうほどの人気画家なのだとか。
銀座ではともかくも、台湾に関してはインフレ必至ですね。
④須田剋太 (1906~1990) の油彩画![]()
司馬遼太郎の紀行文集『街道をゆく』の挿絵を担当したことでも知られる洋画家。
田中田鶴子も須田剋太も、ともにサンパウロ・ビエンナーレに出品経験があります。
鈴木さんによれば、書としても抽象画としても楽しめる作品だそうです。
意外と、畳の部屋にもマッチするとのこと。
⑤香月泰男 (1911~1974) の水彩画![]()
描かれたのは、田中田鶴子の作品とほぼ同時期の1958年。
香月泰男が一番脂が乗っていた時期に描かれた作品です。
香月といえば、シベリア抑留の記憶を基に、
故郷の山口県で制作し続けた 『シベリア・シリーズ』 でお馴染み。
まな板に描かれた鯉も何かを象徴しているのでは、と思わず勘繰ってしまいました。
⑤山本雄教さん (1988~) のフロッタージュ作品![]()
今最も注目を集めている若手美術作家の一人・
山本雄教さんのフロッタージュ作品
《990円札》。
ドットのように見えているのは、実は1円玉。
![]()
麻紙の下には、1円玉が22×45枚、計990枚分敷き詰められています。
それを表面から鉛筆でフロッタージュ、つまり擦って、1万円札の姿を浮かび上がらせた作品です。
990円が1万円に!
確かに、インフレしています (笑)
さて、以上の6点の中から、交換したい作品を1つ選ぶことに。
物故作家は5人、現役の作家は1人。
しかも、僕より歳が若い作家です。
鈴木さんの言うデフレする作品は、ほぼほぼ確定したようなもの。
しかし、それでも残る選択肢は5点。
一番年代が古い作家の作品が高額なのか。
それとも、美術館でよく展覧会が開催される作家の作品が高額なのか。
う~ん。悩みます。
「鈴木さん、もう少し悩んでいいですか?」
「どうぞどうぞ。とに~さんの気が済むまで」
![時計]() 10分経過
10分経過![時計]() 小磯良平の作品が、高そうだなぁ。でも、版画だからなぁ・・・。
小磯良平の作品が、高そうだなぁ。でも、版画だからなぁ・・・。
我が家に香月泰男とかラグーザ玉とかの絵を飾る日が来るなんて、想像したことなかったからなぁ。
いっそ、そのどちらかにしてみようかなぁ。でも、飾るなら、石川欽一郎かなぁ。いや、須田剋太も捨てがたい・・・。悩みすぎて、若干吐き気すらしてきました。
![時計]() さらに、5分経過
さらに、5分経過![時計]()
「・・・よし!決めました!!」
「どれと交換しますか?」
「山本さんの作品で!」
「えっ?!」まさかの展開に、やや驚きを隠せない鈴木さん。
かくいう僕自身も、自分の決断に驚きは隠せません。
「インフレする作品は、たぶん香月泰男とかラグーザ玉とかの作品だと思うんですけど。
散々悩んだ末に、“純粋に部屋に一番飾りたいのはどれ?” と考えると、山本さんの作品でした。
作品として純粋に面白いですし、今後どんな作品を作っていくのかも純粋に気になります。
山本さんは、きっと今後もっと活躍するはず。
現時点では、デフレなのかもしれませんが、
20年後30年後、長いスパンで見れば、一番インフレするかもしれないですし (笑)」
「そういうことなら、山本さんの作品と交換しましょう」
![]()
「ちなみに、ラグーザ玉の作品はおいくらだったのですか?」
「120万円くらいかなぁ」
!!!「ちなみにちなみに、香月泰男の作品は?」
「150万円くらいかなぁ」
!!!!!『あのアートテラーのとに~が、名だたる巨匠の作品を差し置いてまで交換した』 ということが、山本雄教さんの評価に、せめて1円でもプラスになりますように (笑)
![]() 【今回ご協力いただいた画廊】至峰堂画廊
【今回ご協力いただいた画廊】至峰堂画廊住所:東京都中央区銀座6-9-4 銀座小坂ビル4F
1位を目指して、ランキングに挑戦中!
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!![Blogランキングへ]()
![にほんブログ村 美術ブログへ]()





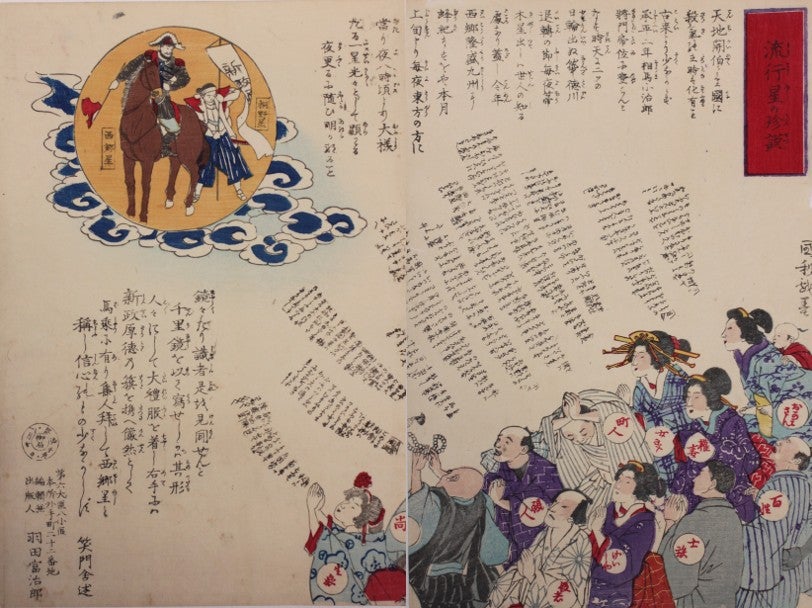




















 )
)











































































































 10分経過
10分経過











































 (星3.5つ)」
(星3.5つ)」











































