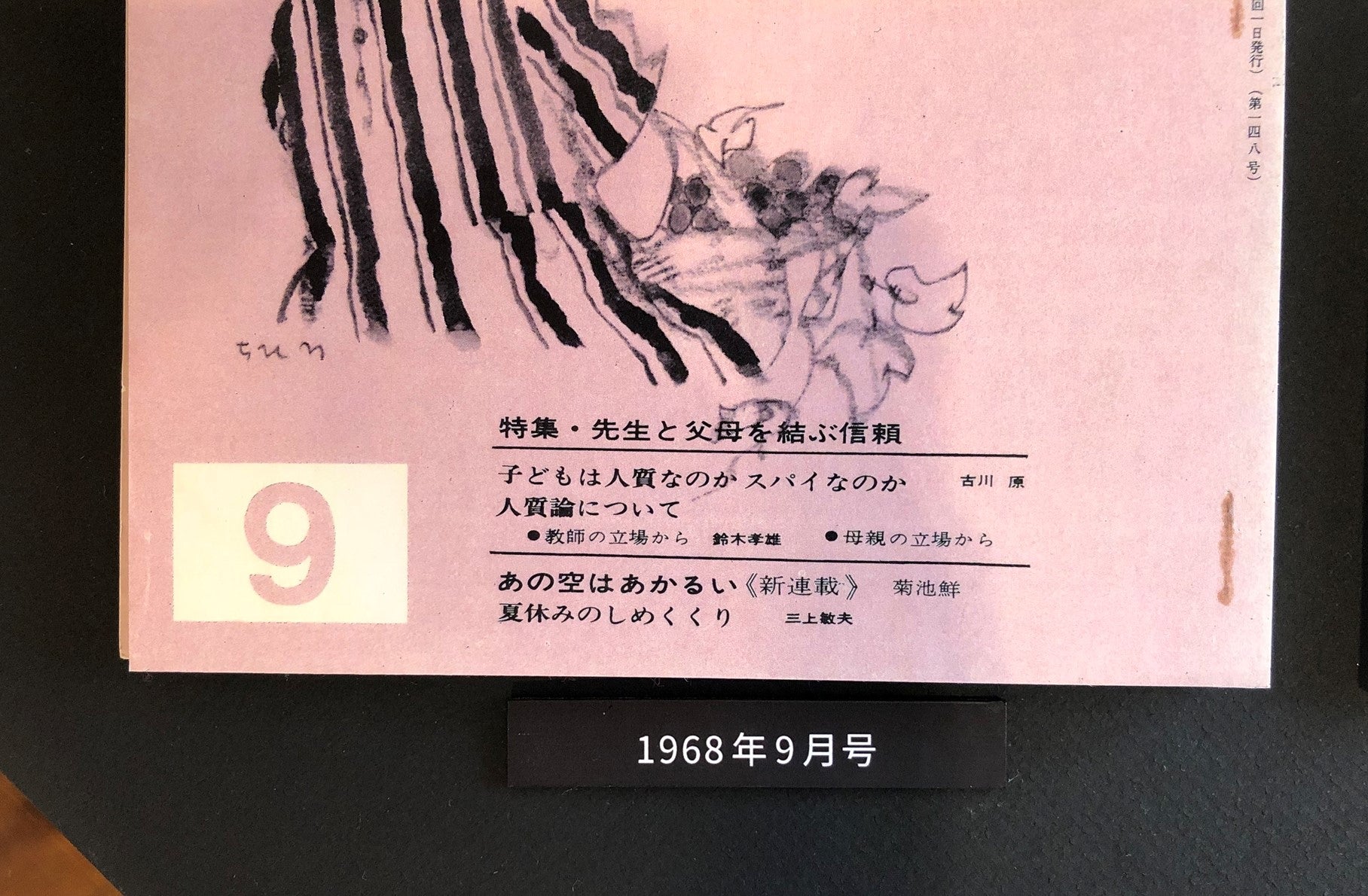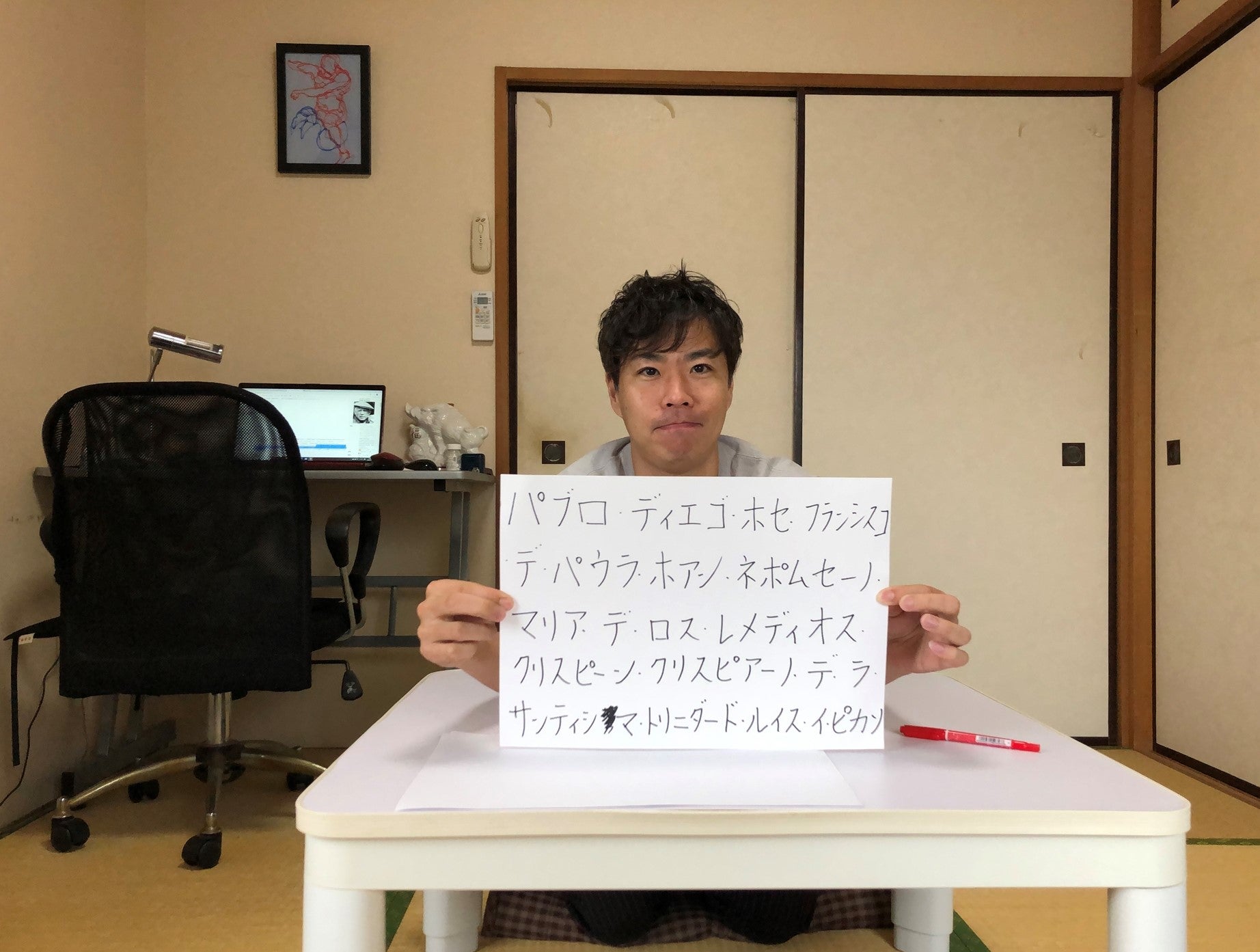千葉県が世界に誇るホキ美術館。
人呼んで、“写実絵画の殿堂” 。
世界でも類を見ない写実絵画専門美術館として、2010年に開館した美術館です。
そんなホキ美術館が悲劇に襲われたのは、昨年10月のこと。
豪雨による水害で、地下2階にある電気設備や収蔵庫、展示室の一部が浸水。
さらに、コレクションのうち約100点の作品も浸水してしまいました。
それにより、復旧が済むまで、休館を余儀なくされています。
なお、現時点で再開時期は未定とのこと。
“ホキ美術館親善大使” としては、いち早い再開を願っております。
出来れば、開館記念日の11月3日には間に合いますように。
さて、そんな中、以前より開催が決定していた、
Bunkamura ザ・ミュージアムでの “超写実絵画の襲来 ホキ美術館所蔵” が、3月18日より開幕。
久しぶりに、ホキ美術館の写実絵画と会える!
・・・・・・・・・・・・・・はずだったのですが。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開幕を見合わせることに。
まさに、踏んだり蹴ったりのホキ美術館でしたが、
なんとか2日遅れで、展覧会を開幕することが出来ました。
![]()
オープン日は、3月20日。
くしくも、僕の誕生日。
自分で言うのもなんですが、さすが、ホキ美術館親善大使です (笑)。
出展作品は、約70点。
上皇ご夫妻の肖像画を描き話題となった野田弘志さんの作品や、
![]()
野田弘志 《聖なるもの THE-Ⅳ》 2013年 油彩・パネル・キャンバス
ホキ美術館きっての人気写実画家・五味文彦さんの作品、
![]()
五味文彦 《いにしえの王は語る》 2018年 油彩・パネル
「このモデルは一体誰?」 という問い合わせが少なくないという生島浩さんの 《5:55》 をはじめ、
![]()
生島浩 《5:55》 2007~2010年 油彩・キャンバス
ホキ美術館コレクションの中でも、特に人気の高い作品の数々が集結していました。
その中には、伝説のあの作品も。
![]()
石黒賢一郎 《存在の在処》 2001~2011年 油彩・パネル・綿布
石黒賢一郎さんの 《存在の在処》 です。
黒板の描写があまりにリアルなため、触ろうとする人が続出。
そのため、アクリルで覆わざるを得なくなったというエピソードを持つ作品です。
エピソードとしては、興味深いですが。
よくよく考えたら、せっかく剥き出しの状態で観れてたものが、
アクリル越しでの鑑賞となってしまったことは、鑑賞する側としては残念な限り。
誰ですか、触ろうとした人は?!
もちろん黒板もチョークも油彩で描かれているわけですが、
仮にチョークで描かれていたからといって、そもそも作品に触るのはNGです。
また、ホキ美術館にとって最も重要な画家、
森本草介さんの作品ももちろん出展されていました。
![]()
森本草介 《未来》 2011年 油彩・キャンバス
こちらの 《未来》 は、2011年3月11日の大震災の時に、ちょうど制作中だったという一枚。
他の描きかけの作品は、イーゼルから落ちてカンヴァスが破れてしまったそうですが、
この作品は、パレットの上に倒れるも、絵の具がべったりと付いただけで済んだとのこと。
震災を耐えたことから、《未来》 というタイトルが付けられたのだそうです。
なお、展覧会には、森本草介さんの 《横になるポーズ》 も出展されていました。
実は、この絵は、ホキ美術館コレクション第一号となった記念すべき作品。
ホキ美術館の創設者、保木将夫さんが写実絵画に魅了されるきっかけとなった作品です。
もし、この絵との出逢いがなかったら、ホキ美術館は存在していなかったかもしれません。
さてさて、これは完全に僕の推測でしかないのですが。
おそらく、当初予定されていた出展作品から変更があったのではなかろうか?
そう考えざるを得ないほど、ベストofベストの名品が揃い踏みでした。
昨年の水害が無ければ、今頃、ホキ美術館は普通に開館していたはず。
これほどまでに名品がまとまった形で外部に貸し出されていたら、
ホキ美術館を訪れた人が、あれも無いこれも無いとガッカリしてしまっていたことでしょう。
しかし、残念ながら、ホキ美術館は現在臨時休館中。
そこで、急遽、当初の予定よりももっと一軍メンバーを、
Bunkamura ザ・ミュージアムに送り込んでくれたような気がします。
何はともあれ、千葉よりはアクセスしやすい渋谷の地で、
ホキ美術館のベストofベストコレクションが観られるのは、奇跡としか言いようがありません!
是非、この機会をお見逃しなく。
![星]()
![星]()
![星]()
そして、ホキ美術館が無事に再オープンした暁には、
千葉にあるホキ美術館のほうにも、足を運んで頂けたら幸いです。
┃会期:2020年3月20日(金・祝)〜5月11日(月・祝)
┃会場:Bunkamura ザ・ミュージアム
┃https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/20_choshajitsu/
1位を目指して、ランキングに挑戦中。
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!
![Blogランキングへ]()
![にほんブログ村 美術ブログへ]()
人呼んで、“写実絵画の殿堂” 。
世界でも類を見ない写実絵画専門美術館として、2010年に開館した美術館です。
そんなホキ美術館が悲劇に襲われたのは、昨年10月のこと。
豪雨による水害で、地下2階にある電気設備や収蔵庫、展示室の一部が浸水。
さらに、コレクションのうち約100点の作品も浸水してしまいました。
それにより、復旧が済むまで、休館を余儀なくされています。
なお、現時点で再開時期は未定とのこと。
“ホキ美術館親善大使” としては、いち早い再開を願っております。
出来れば、開館記念日の11月3日には間に合いますように。
さて、そんな中、以前より開催が決定していた、
Bunkamura ザ・ミュージアムでの “超写実絵画の襲来 ホキ美術館所蔵” が、3月18日より開幕。
久しぶりに、ホキ美術館の写実絵画と会える!
・・・・・・・・・・・・・・はずだったのですが。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開幕を見合わせることに。
まさに、踏んだり蹴ったりのホキ美術館でしたが、
なんとか2日遅れで、展覧会を開幕することが出来ました。

オープン日は、3月20日。
くしくも、僕の誕生日。
自分で言うのもなんですが、さすが、ホキ美術館親善大使です (笑)。
出展作品は、約70点。
上皇ご夫妻の肖像画を描き話題となった野田弘志さんの作品や、

野田弘志 《聖なるもの THE-Ⅳ》 2013年 油彩・パネル・キャンバス
ホキ美術館きっての人気写実画家・五味文彦さんの作品、

五味文彦 《いにしえの王は語る》 2018年 油彩・パネル
「このモデルは一体誰?」 という問い合わせが少なくないという生島浩さんの 《5:55》 をはじめ、

生島浩 《5:55》 2007~2010年 油彩・キャンバス
ホキ美術館コレクションの中でも、特に人気の高い作品の数々が集結していました。
その中には、伝説のあの作品も。

石黒賢一郎 《存在の在処》 2001~2011年 油彩・パネル・綿布
石黒賢一郎さんの 《存在の在処》 です。
黒板の描写があまりにリアルなため、触ろうとする人が続出。
そのため、アクリルで覆わざるを得なくなったというエピソードを持つ作品です。
エピソードとしては、興味深いですが。
よくよく考えたら、せっかく剥き出しの状態で観れてたものが、
アクリル越しでの鑑賞となってしまったことは、鑑賞する側としては残念な限り。
誰ですか、触ろうとした人は?!
もちろん黒板もチョークも油彩で描かれているわけですが、
仮にチョークで描かれていたからといって、そもそも作品に触るのはNGです。
また、ホキ美術館にとって最も重要な画家、
森本草介さんの作品ももちろん出展されていました。

森本草介 《未来》 2011年 油彩・キャンバス
こちらの 《未来》 は、2011年3月11日の大震災の時に、ちょうど制作中だったという一枚。
他の描きかけの作品は、イーゼルから落ちてカンヴァスが破れてしまったそうですが、
この作品は、パレットの上に倒れるも、絵の具がべったりと付いただけで済んだとのこと。
震災を耐えたことから、《未来》 というタイトルが付けられたのだそうです。
なお、展覧会には、森本草介さんの 《横になるポーズ》 も出展されていました。
実は、この絵は、ホキ美術館コレクション第一号となった記念すべき作品。
ホキ美術館の創設者、保木将夫さんが写実絵画に魅了されるきっかけとなった作品です。
もし、この絵との出逢いがなかったら、ホキ美術館は存在していなかったかもしれません。
さてさて、これは完全に僕の推測でしかないのですが。
おそらく、当初予定されていた出展作品から変更があったのではなかろうか?
そう考えざるを得ないほど、ベストofベストの名品が揃い踏みでした。
昨年の水害が無ければ、今頃、ホキ美術館は普通に開館していたはず。
これほどまでに名品がまとまった形で外部に貸し出されていたら、
ホキ美術館を訪れた人が、あれも無いこれも無いとガッカリしてしまっていたことでしょう。
しかし、残念ながら、ホキ美術館は現在臨時休館中。
そこで、急遽、当初の予定よりももっと一軍メンバーを、
Bunkamura ザ・ミュージアムに送り込んでくれたような気がします。
何はともあれ、千葉よりはアクセスしやすい渋谷の地で、
ホキ美術館のベストofベストコレクションが観られるのは、奇跡としか言いようがありません!
是非、この機会をお見逃しなく。



そして、ホキ美術館が無事に再オープンした暁には、
千葉にあるホキ美術館のほうにも、足を運んで頂けたら幸いです。
┃会期:2020年3月20日(金・祝)〜5月11日(月・祝)
┃会場:Bunkamura ザ・ミュージアム
┃https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/20_choshajitsu/
1位を目指して、ランキングに挑戦中。
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!