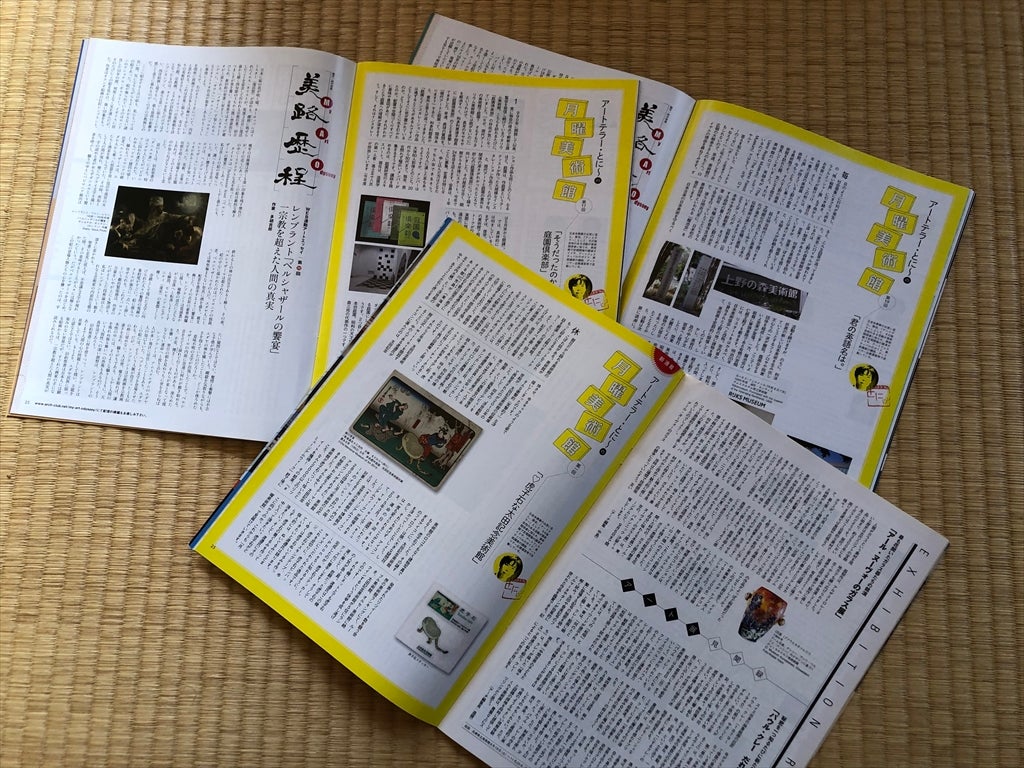ここ最近、テレビ番組を観てる際に、
人がたくさん集まっているシーンが映ると
「密だなぁ」 と感じてしまうことが多々あります。
緊急事態宣言が発令される前に収録されたものだと、
頭ではもちろん理解しているのですが、どうしても感じてしまうのです。
おそらく、しばらくはこの感覚と付き合うことになるのでしょう。
・・・・・・・・・・であるならば。
今後しばらくは、オランダの集団肖像画や、
![]()
ミケランジェロの 《最後の審判》 を鑑賞する際に、
![]()
「密だなぁ」 と感じてしまうのでしょう。
昨年までは、そんな感想を一切抱かなかったというのに。
レオナルド・ダ・ヴィンチの 《最後の晩餐》 を鑑賞する際にいたっては、
![]()
「一緒に会食に行く弟子の数を減らさないと」 とか、
「このお店は、ちゃんと20時に閉まるのかな?」 とか。
そんな感想を抱いてしまうかもしれません。
ということで今回は、美術界における密な作品を集めてみました。
都知事でなくとも、「密です!」 と思わず言いたくなる絵画の数々です。
●ウジェーヌ・ヴーダン 《浜辺の風景》
![]()
今も昔も、人は浜辺に集まるもの。
湘南のビーチも大変なことになっていましたが、
フランスのこのビーチにも、やはり大変なことになっていたのでしょうか。
●ヤン・ブリューゲル(父) 《山上の垂訓》
![]()
何かのフェスな??
そう思ってしまうくらいに人が集まっています。
よく見ると、青いものを身に付けた人が目立ちますね。
彼らの推しメンのイメージカラーは、きっと青なのでしょう。
●エイドリアン・ファン・デ・ヴェンネ 《Fishing for souls》
![]()
見渡す限り、人・人・人。
コミケの行列を彷彿とさせるものがあります。
船の中も、とんでもなく密集状態です。
乗船率は間違いなく200%を超えていますね。
![]()
![]()
●デニス・ファン・アルスロート
《ブリュッセルのオメガングもしくは鸚鵡の祝祭:職業組合の行列》
![]()
![]()
2018年に開催された “プラド美術館展” で出合った衝撃的な作品。
外も密。内も密。
クラスターになるのは確実です。
●橋本貞秀 《東都両国ばし夏景色》
![]()
日本の美術界にも、もちろん “密ですアート” はあります。
その中でも群を抜いて、密なのがこちらの浮世絵。
隅田川は、舟でかなり密に。
さらに、橋の上をよく見てみると・・・・・・
![]()
たくさんの人が描かれているのがわかります。
決して、ポップコーンの種ではありません。
これだけ密集していると、もはやコロナとか関係なく不安になります。
●《阿弥陀聖衆来迎図》
![]()
たくさんの菩薩を引き連れて、阿弥陀様が迎えに来てくれる。
これまでであれば、それを有難く感じたのでしょうが。
今だけは、「いやいやいや、そんなに大勢で来ないでよ (汗)」 となること必至です。
阿弥陀様も集団感染にはお気を付けくださいませ。
●ヘクター・ジャコメリ 《鳥の止まり木》
![]()
記事を読んでいる方に、
「密だなぁ」 と不安を煽ってばかりいるのもなんなので。
ここらで可愛らしい “密” をご紹介しましょう。
鳥の世界には、ソーシャルディスタンスはないようです。
●ビンビ(バルトロメオ・デル・ビンボ) 《さくらんぼ》
![]()
密な静物画ばかりを描く画家。
それが、バルトロメオ・デル・ビンボ。通称、ビンビ。
さくらんぼが、密。
密すぎて、観てるだけで胸焼けがしてきました。
他にも、まだまだ “密ですアート” はありますが。
“密ですアート” が密になるのもなんなので、本日はこれまで。
皆さま、しばらく密を避けて、乗り切りましょう。
1位を目指して、ランキングに挑戦中。
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!
![Blogランキングへ]()
![にほんブログ村 美術ブログへ]()
人がたくさん集まっているシーンが映ると
「密だなぁ」 と感じてしまうことが多々あります。
緊急事態宣言が発令される前に収録されたものだと、
頭ではもちろん理解しているのですが、どうしても感じてしまうのです。
おそらく、しばらくはこの感覚と付き合うことになるのでしょう。
・・・・・・・・・・であるならば。
今後しばらくは、オランダの集団肖像画や、

ミケランジェロの 《最後の審判》 を鑑賞する際に、

「密だなぁ」 と感じてしまうのでしょう。
昨年までは、そんな感想を一切抱かなかったというのに。
レオナルド・ダ・ヴィンチの 《最後の晩餐》 を鑑賞する際にいたっては、

「一緒に会食に行く弟子の数を減らさないと」 とか、
「このお店は、ちゃんと20時に閉まるのかな?」 とか。
そんな感想を抱いてしまうかもしれません。
ということで今回は、美術界における密な作品を集めてみました。
都知事でなくとも、「密です!」 と思わず言いたくなる絵画の数々です。
●ウジェーヌ・ヴーダン 《浜辺の風景》

今も昔も、人は浜辺に集まるもの。
湘南のビーチも大変なことになっていましたが、
フランスのこのビーチにも、やはり大変なことになっていたのでしょうか。
●ヤン・ブリューゲル(父) 《山上の垂訓》

何かのフェスな??
そう思ってしまうくらいに人が集まっています。
よく見ると、青いものを身に付けた人が目立ちますね。
彼らの推しメンのイメージカラーは、きっと青なのでしょう。
●エイドリアン・ファン・デ・ヴェンネ 《Fishing for souls》

見渡す限り、人・人・人。
コミケの行列を彷彿とさせるものがあります。
船の中も、とんでもなく密集状態です。
乗船率は間違いなく200%を超えていますね。


●デニス・ファン・アルスロート
《ブリュッセルのオメガングもしくは鸚鵡の祝祭:職業組合の行列》


2018年に開催された “プラド美術館展” で出合った衝撃的な作品。
外も密。内も密。
クラスターになるのは確実です。
●橋本貞秀 《東都両国ばし夏景色》

日本の美術界にも、もちろん “密ですアート” はあります。
その中でも群を抜いて、密なのがこちらの浮世絵。
隅田川は、舟でかなり密に。
さらに、橋の上をよく見てみると・・・・・・

たくさんの人が描かれているのがわかります。
決して、ポップコーンの種ではありません。
これだけ密集していると、もはやコロナとか関係なく不安になります。
●《阿弥陀聖衆来迎図》

たくさんの菩薩を引き連れて、阿弥陀様が迎えに来てくれる。
これまでであれば、それを有難く感じたのでしょうが。
今だけは、「いやいやいや、そんなに大勢で来ないでよ (汗)」 となること必至です。
阿弥陀様も集団感染にはお気を付けくださいませ。
●ヘクター・ジャコメリ 《鳥の止まり木》

記事を読んでいる方に、
「密だなぁ」 と不安を煽ってばかりいるのもなんなので。
ここらで可愛らしい “密” をご紹介しましょう。
鳥の世界には、ソーシャルディスタンスはないようです。
●ビンビ(バルトロメオ・デル・ビンボ) 《さくらんぼ》

密な静物画ばかりを描く画家。
それが、バルトロメオ・デル・ビンボ。通称、ビンビ。
さくらんぼが、密。
密すぎて、観てるだけで胸焼けがしてきました。
他にも、まだまだ “密ですアート” はありますが。
“密ですアート” が密になるのもなんなので、本日はこれまで。
皆さま、しばらく密を避けて、乗り切りましょう。
1位を目指して、ランキングに挑戦中。
下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!